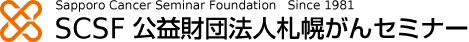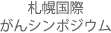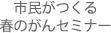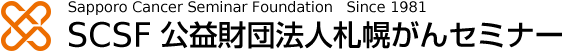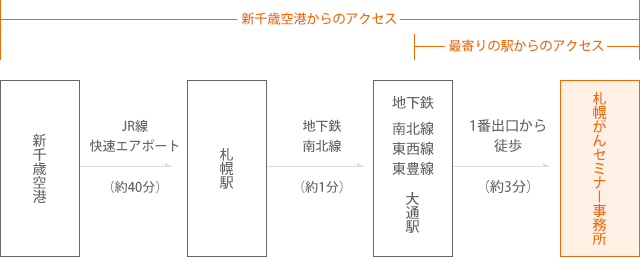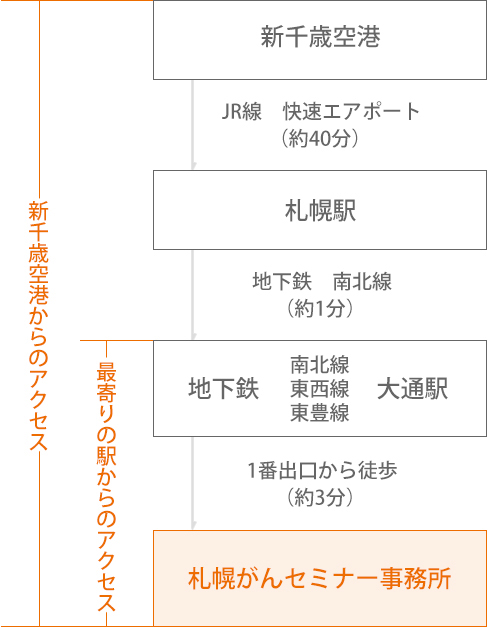肺がんでは遺伝子変異の種類によってそれぞれの分子標的治療の使い分けが行われ一定の効果が示されるようになりました。つまり「ゲノム医療」を駆使してがん治療の先端を走っている一番の対象臓器は肺がんのようです。とくに最近の肺がんの治療成績が随分とよくなってきましたね。なぜ肺がんがとくにゲノム医療の対象になり得ているのでしょうか?
上皮成長因子受容体(EGFR)は正常な細胞の表面にも存在するタンパク質です。受容体という名前からもわかるように、正常細胞ではこれに対応する成長因子(上皮成長因子EGF等)が結合した時にだけ、細胞増殖のシグナルを細胞核へ伝えるのです。このような細胞増殖は発生成長や創傷の治癒の過程では必須ですが、役目を終えた後は増殖はとまります。
一部の肺がんではこのEGFR遺伝子に突然変異がおこることで、増殖因子の結合なしに常にスイッチが入った状態となっています。活性化されたEGFRはチロシンというアミノ酸をリン酸化する酵素(チロシンキナーゼ)としてはたらくことで次々と下流の経路のスイッチをいれていきます。即ち、このような肺がんは増殖や生存をほとんどこのEGFR経路に依存しており、このような状態をがん遺伝子依存状態と呼びます。
このようながんにEGFRチロシンキナーゼを阻害する薬物(ゲフィチニブ等5種類あります)を投与すると、この経路が遮断され細胞死が誘導されるわけです。その後、肺がんにおいてALK、 ROS1、 BRAFといった遺伝子の異常でも同様のがん遺伝子依存状態となることが発見され、それぞれの遺伝子の特異的な阻害剤が治療として用いられるようになっています。従って、がん組織をとってきて遺伝子検査をおこなうことが治療方針決定のために重要です。これらの遺伝子異常は肺がんの70%を占める腺がんに限られており、腺がんの中でのおよその頻度はEGFR 50%、ALK 5%、ROS1 2%、BRAF 1%程度です。これらの異常を効率よくみつけるために次世代DNAシーケンシング技術が使われつつあり、このようなヒト遺伝子情報(ゲノム)にもとづくがん診療をゲノム医療と呼んでいます。
がん遺伝子依存状態は慢性骨髄性白血病や消化管間質腫瘍にも存在し、それ特異的な治療薬があります。乳癌ではHER2という遺伝子が少し弱い依存状態をつくっています。しかし、大腸がん、胃がんといったがんではがん遺伝子依存状態をひきおこす遺伝子はほとんどありません。このようながんの種類による差の原因はまだよくわかっていません。
近畿大学医学部呼吸器外科主任教授 光冨 徹哉
出典 The Way Forward No.16, 2019年